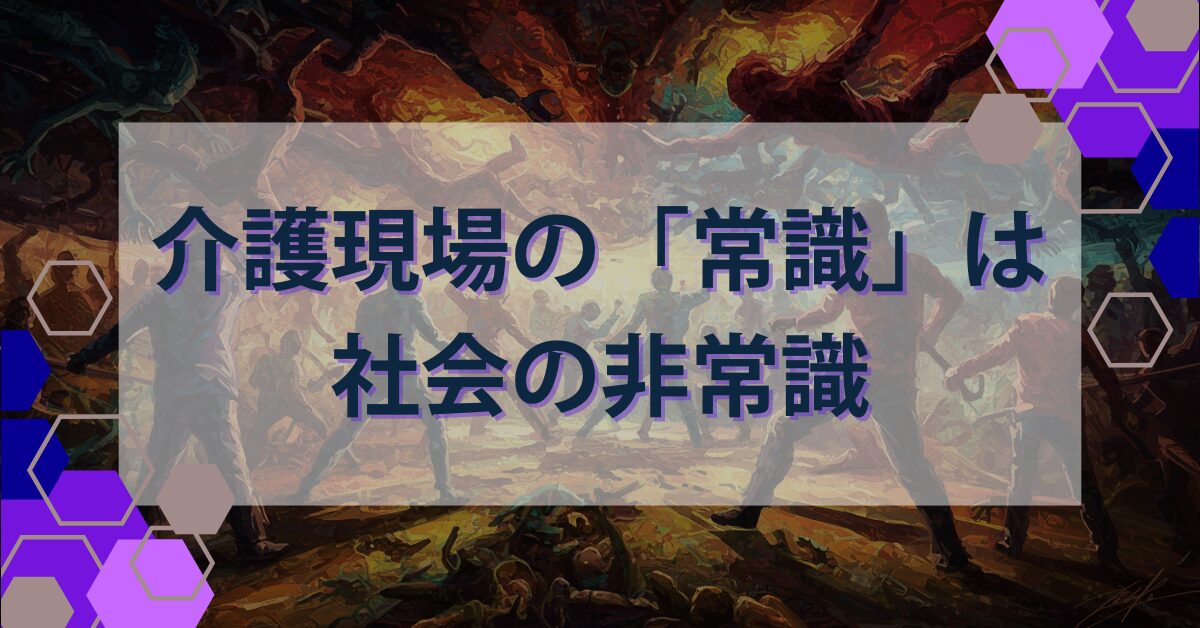「摘便、点滴の針抜き…それが日常でした」
先日、X(旧Twitter)に届いた一件のDM。
そこには、介護現場で働く方からの切実な訴えが綴られていました。
長年、特別養護老人ホームで働いてきたというその方は、日々の業務の中で、医療行為の線引きに深く悩んでいるといいます。
ベテラン職員の中には、『昔からやっているから大丈夫』と、摘便や褥瘡の処置を日常的に行っている人がいます。
でも、私は法的なリスクを考えると、どうしても抵抗があるんです
上司に相談しても、「他の職員もやっていることだから」と明確な指示は得られず、看護師に確認しても、「状況による」といった曖昧な返答ばかり。
その方は、誰に相談すれば良いのか分からず、一人で抱え込んでいるといいます。
これは、決して他人事ではありません。
介護現場における医療行為の線引き問題は、多くの施設で曖昧なまま放置され、働く人々を苦しめています。
人手不足、経験豊富な職員の慣習、曖昧な指示、そして組織としての責任感の欠如。
これらの要因が複雑に絡み合い、介護現場は医療行為の線引きがあいまいな状況を生み出しているのです。
この記事では、介護現場で働く方から寄せられたDMの内容を基に、医療行為の線引き問題について深く掘り下げていきます。
記事監修者

堀池和将
~経歴~
特別養護老人ホーム勤務(ユニットリーダー)
サービス付き高齢者住宅勤務(サービス提供責任者・訪問介護管理者・施設長)
~保有資格~
介護福祉士
Contents
介護現場の闇、摘便と針抜きが横行する現実

DMで寄せられた特別養護老人ホームでは、摘便や褥瘡の処置といった医療行為が日常的に行われていました。
長年の経験を持つベテラン職員たちは、「昔からやっているから大丈夫」と、これらの行為を慣習化していました。
しかし、こうした行為は法的なリスクを伴い、利用者だけでなく職員自身の安全も脅かす可能性があります。
ベテラン職員の「昔からの慣習」に潜むリスク
「昔からやっているから」「これくらい大丈夫」。
ベテラン職員のこうした言葉は、一見すると経験に基づいた自信のように聞こえます。
しかし、医療行為の線引きがあいまいなまま行われるこれらの行為は、大きなリスクを伴います。
摘便や褥瘡の処置は、本来医師や看護師が行うべき医療行為です。
知識や技術を持たない介護士が行うことは、利用者の身体に深刻なダメージを与える可能性があります。
また、法的な責任を問われる可能性もあり、職員自身のキャリアにも傷をつけることになりかねません。
「これくらい大丈夫」が招く、取り返しのつかない事態
「これくらい大丈夫」という安易な判断が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。
例えば、摘便の際に利用者の肛門を傷つけてしまったり、褥瘡の処置で感染症を引き起こしてしまったりするケースが考えられます。
こうした事態は、利用者の尊厳を深く傷つけるだけでなく、最悪の場合、命に関わることもあります。
また、施設全体の信頼を失墜させ、運営にも大きな影響を与える可能性があります。
北海道・東北・新潟エリアに特化した介護職専門の転職支援エージェント
-

-
【ほっ介護の裏側を独自取材】体験談・良い評判から悪い口コミまで徹底分析!
あなたは今、そんな悩みを抱えていませんか? 介護職専門の転職エージェント「ほっ介護」は、そんなあなたの悩みを解決する心強いパートナーです。地域密着型の豊富な求人情報はもちろん、経験豊富なコンサルタント ...
続きを見る
なぜ?医療行為の線引きがあいまいな現場

介護現場における医療行為の線引きがあいまいな背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。
人手不足、経験豊富な職員の慣習、曖昧な指示、そして組織としての責任感の欠如。
これらの要因が重なり合い、介護現場は医療行為の線引きがあいまいな状況を生み出しています。
人手不足と曖昧な指示が生む、介護士の葛藤
深刻な人手不足は、介護現場に大きな負担を与えています。
限られた人員で多くの業務をこなさなければならない状況下では、医療行為の線引きがあいまいになりがちです。
また、上司や看護師からの指示が曖昧な場合、介護士はどのように判断すれば良いか迷ってしまいます。
「他の職員もやっているから」「状況による」といった曖昧な返答は、介護士の不安を増幅させるばかりです。
介護士たちは、法的なリスクを認識しながらも、目の前の業務をこなさなければならないというジレンマに苦しんでいます。
「見て見ぬふり」が常態化する、組織の責任
医療行為の線引きがあいまいな状況が常態化している背景には、組織としての責任感の欠如も考えられます。
施設側が明確なガイドラインを示さず、職員の教育や研修も不十分な場合、医療行為に関する問題は放置されがちです。
また、問題が発覚しても「見て見ぬふり」をするような組織風土も、状況を悪化させる要因となります。
施設長や管理職は、法的リスクを認識し、職員が安心して働ける環境を整備する責任があります。
知らなかったでは済まされない、法的リスク

介護現場における医療行為の線引きがあいまいなまま放置されている現状は、法的リスクを無視できません。
介護士が医療行為を行った場合、医師法違反に問われる可能性があります。
また、利用者に損害を与えた場合には、損害賠償責任を負うこともあります。
医師法違反、介護士が背負う重すぎる責任
医師法第17条は、「医師でなければ、医業をしてはならない」と定めています。
つまり、医師免許を持たない介護士が医療行為を行うことは、原則として違法です。
摘便や褥瘡の処置など、医療行為に該当する行為を介護士が行った場合、医師法違反に問われる可能性があります。
違反した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、業務上過失致死傷罪に問われる可能性もあり、その責任は非常に重いです。
あなたの家族が被害者になる可能性も
医療行為の線引きがあいまいな状況は、利用者だけでなく、その家族にも大きな不安を与えます。
もし、あなたの家族が介護施設で不適切な医療行為を受け、健康被害に遭ってしまったらどうでしょうか?
想像してみてください。大切な家族が苦しんでいる姿を目の当たりにし、深い悲しみと怒りを感じるでしょう。
また、介護施設への信頼を失い、今後の生活に大きな不安を抱えることになるでしょう。
医療行為に関する問題は、決して他人事ではありません。
変えるのは私たち、解決への道筋

医療行為の線引き問題を解決するためには、施設側と介護士双方の意識改革が不可欠です。
施設側は明確なガイドラインを示し、介護士は正しい知識と判断力を身につける必要があります。
施設側の責任、明確なガイドラインの必要性
施設側は、医療行為に関する明確なガイドラインを作成し、職員に周知徹底する必要があります。
ガイドラインには、医療行為と判断される具体的な行為、介護士が行える範囲、判断に迷った場合の相談窓口などを明記します。
また、定期的な研修や勉強会を開催し、職員の知識向上を図ることも重要です。
さらに、医療行為に関する相談窓口を設置し、職員が気軽に相談できる体制を整えることも求められます。
施設長や管理職は、法的リスクを認識し、職員が安心して働ける環境を整備する責任があります。
介護士の意識改革、正しい知識と判断力
介護士自身も、医療行為に関する正しい知識を身につける必要があります。
医師法などの関連法規を理解し、医療行為と判断される行為を把握することが重要です。
また、日々の業務の中で、医療行為に該当する可能性のある行為に遭遇した場合は、安易な判断をせず、必ず上司や看護師に相談するようにしましょう。
経験豊富なベテラン職員であっても、自己判断は禁物です。
常に謙虚な姿勢で学び続け、正しい知識と判断力を養うことが、利用者と自身の安全を守ることに繋がります。
未来の介護のために、今私たちにできること

医療行為の線引き問題は、介護現場だけでなく、私たち社会全体で考えていくべき課題です。
一人ひとりが問題を認識し、行動することで、より良い介護現場を作ることができます。
一人ひとりの行動が、より良い現場を作る
施設側は、明確なガイドラインの作成や研修の実施など、組織としての責任を果たす必要があります。
介護士は、正しい知識と判断力を身につけ、常に謙虚な姿勢で学び続けることが大切です。
そして、私たち一人ひとりが、介護現場で働く人たちを尊重し、支え合う気持ちを持つことが、より良い介護現場を作るために不可欠です。
未来の介護を、私たちで創りましょう
高齢化が進む日本において、介護は誰もが関わる可能性のある身近な問題です。
医療行為の線引き問題を解決し、利用者も介護士も安心して過ごせる環境を作ることは、未来の介護をより良くするために、今私たちにできることです。
私たち一人ひとりの意識と行動が、未来の介護を大きく変える力となります。
未来の介護を、私たちみんなで創りましょう。
こちらもCHECK
-

-
介護職が利用できる転職エージェントと求人サイトの徹底比較
ハロー介護職! あなたは日本における介護職専門の転職サイトや転職エージェントは、大体何社ほどあるか知っていますか?大小さまざまな規模のものを含めると約30~50社ほど存在すると言われています。これから ...
続きを見る
参考:https://www.nippku.ac.jp/license/cw/medical-practice/
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0325-17c.pdf
https://www.yurokyo.or.jp/info/view/4336