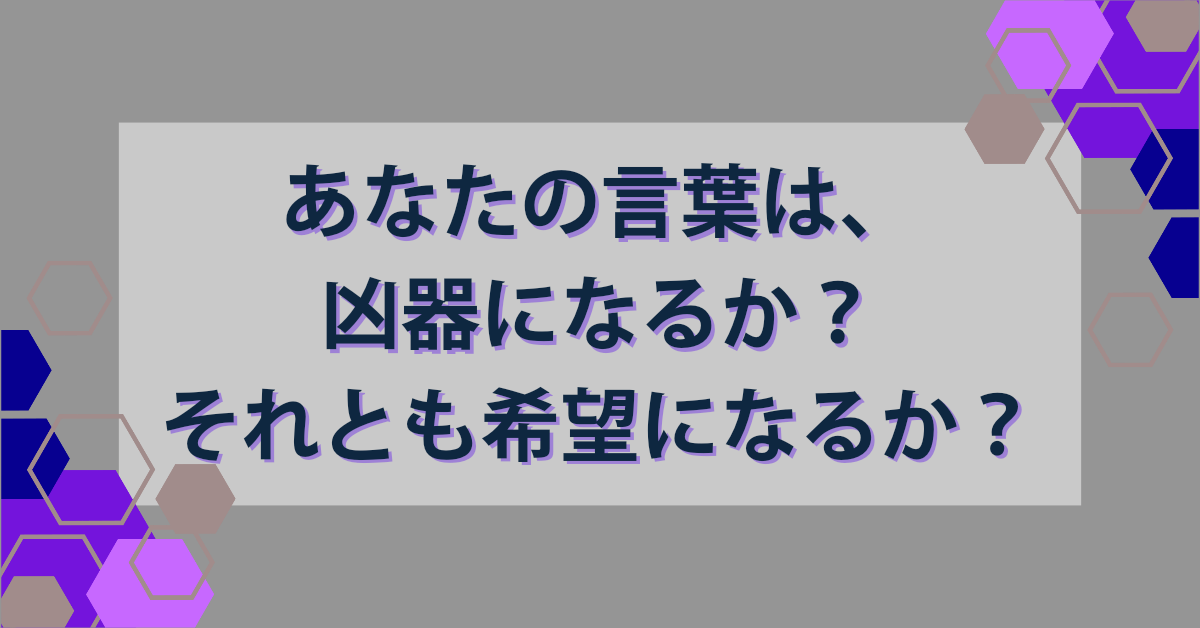「さっきも言いましたよ!」
認知症の利用者様へ放った、あの時の私の言葉。
それは、まるで鋭い刃物のように、利用者様の心を深く傷つけてしまいました。
あの時、私は言葉が凶器になることを知り、自分の未熟さを深く後悔しました。
しかし、過去を悔やんでばかりはいられません。
あの出来事から学び、私は言葉と向き合い続けています。
なぜなら、言葉は人を傷つけるだけでなく、温かく包み込み、励ます力も持っていると信じているからです。
この記事では、私が体験した「言葉の凶器」の恐ろしさと、そこから得た教訓を赤裸々に語ります。
そして、NGワードを避けるための具体的な方法や、利用者様、ご家族との心温まるコミュニケーション術もご紹介します。
この記事を読むことで、あなたは言葉の選び方一つで、相手の心をどれほど深く傷つけ、また温かくできるのかを理解できるでしょう。
そして、明日からの介護現場で、より良いコミュニケーションを築くためのヒントを得られるはずです。
さあ、私たちと一緒に、言葉の力を信じ、より良い介護現場を目指しませんか?
この記事でわかること
- 介護現場で避けるべきNGワードと適切な言い換え表現
- NGワードを使ってしまった際の適切な対処法と再発防止策
- 利用者様やご家族と円滑なコミュニケーションを築くための具体的な方法
この記事を書いた人

ハロー介護職
適応障害と付き合いつつ、日々介護現場で高齢者と向き合う一人の介護職。
X(旧Twitter)やTikTokで自信の介護感や疑問を投げかける活動をしています。
介護系記事監修の仕事もしています。
お仕事の相談はX(旧Twitter)のDMにて受け付けております。
お気軽にご相談ください。
Contents
介護現場でNGワードを使ってしまうことによる影響

介護現場における言葉遣いは、利用者様やそのご家族との信頼関係を築く上で非常に重要です。
しかし、不適切な言葉、いわゆるNGワードを使ってしまうと、様々な悪影響が生じる可能性があります。
ここでは、NGワードがもたらす具体的な影響について解説します。
利用者や家族との信頼関係を損なう
NGワードは、利用者様やご家族を不快にさせ、尊厳を傷つけることがあります。
例えば、タメ口や命令口調は、相手を見下している印象を与え、信頼関係を大きく損なうでしょう。
信頼関係が崩れると、利用者様は介護サービスを拒否したり、ご家族は施設への不信感を募らせたりする可能性があります。
その結果、介護サービスの質が低下し、利用者様の心身状態にも悪影響を及ぼすかもしれません。
介護職員自身の評価低下とキャリアへ影響を及ぼす
介護職員がNGワードを使うことは、自身の評価を下げることにも繋がります。
周囲からの信頼を失い、キャリアアップの機会を逃す可能性もあるでしょう。
また、利用者様やご家族からのクレームは、精神的な負担となり、仕事へのモチベーション低下にも繋がりかねません。
プロ意識を持ち、常に丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。
介護施設の評判低下と社会的信用の失墜につながる
NGワードの使用は、介護施設全体の評判を大きく損なう可能性があります。
インターネットやSNSで情報が拡散されやすい現代社会において、施設のイメージダウンは利用者の減少に繋がりかねません。
また、地域社会からの信頼を失うことで、施設の運営自体が困難になることも考えられます。
施設全体の質を維持するためにも、職員一人ひとりが言葉遣いに注意を払う必要があるでしょう。
虐待につながる可能性がある
NGワードは、言葉による虐待、いわゆる「スピーチロック」に該当する可能性があります。
例えば、利用者様の行動を制限したり、尊厳を傷つけるような言葉は、精神的な苦痛を与え、虐待とみなされることがあります。
言葉遣いは、身体的な虐待と同様に、利用者様の心に深い傷を残す可能性があることを認識しなければなりません。
筆者が実際に介護現場で言ってしまったNGワード

介護現場で働く中で、私は言葉が持つ力、そしてその責任の重さを痛感する出来事がありました。
それは、私の未熟な言葉が、利用者様を深く傷つけてしまった経験です。
この体験を通して、私は言葉の選び方一つで、相手の心を温かくすることも、深く傷つけることもできることを学びました。
この経験を、同じように言葉と向き合う介護職員の方々、そしてこれから介護の道を目指す方々に共有したいと思います。
「もう、あなたの顔も見たくない」あの時、私の言葉は凶器だった
あの日、私はいつものように利用者様のAさんの居室を訪れました。
Aさんは認知症を患っており、同じ質問を何度も繰り返すことがありました。
その日も、「今日は何日?」「ご飯は何?」「家族はいつ来るの?」と、同じ質問を何度も繰り返していました。
私は、何度も答えるうちに、次第にイライラが募り、つい語気を強めてしまいました。
「Aさん、さっきも言いましたよ!もう何度も…」
その瞬間、Aさんの表情が曇り、目に涙が溢れました。
そして、震える声でこう呟いたのです。
「もう、あなたの顔も見たくない…」
その言葉は、まるで鋭い刃物のように、私の胸に突き刺さりました。
Aさんの悲しそうな表情、震える声、そして、私を拒絶する言葉。
そのすべてが、私の心に深く刻み込まれました。
私は、自分の言葉が、Aさんの心をどれほど深く傷つけたのかを、その時初めて痛感しました。
Aさんは、認知症によって記憶が曖昧になり、不安や孤独を感じていました。
私に何度も同じ質問を繰り返したのは、不安を解消し、安心感を求めていたからかもしれません。
それなのに、私はAさんの気持ちに寄り添うことなく、自分の感情を優先してしまったのです。
あの時、私は介護職員として、あるまじき行為をしてしまいました。
Aさんの心を傷つけ、信頼を裏切ってしまったのです。
私は、Aさんに心から謝罪しました。
そして、二度とAさんを傷つけないために、Aさんの気持ちに寄り添い、根気強く接することを誓いました。
それ以来、私はどんな時も感情的にならず、常に相手の気持ちに寄り添うことを心がけています。
Aさんのように、言葉をうまく扱えない方、また、言葉をうまく扱えたとしても、その言葉で、相手の心を深く傷つけてしまうということを、私は身をもって知りました。
言葉は、人を傷つける凶器にもなり得るのです。
だからこそ、私たちは、言葉の重みを深く理解し、常に相手を思いやる言葉を選ぶ必要があるのです。
介護現場で避けるべきNGワード具体例と今すぐ使える言い換え集
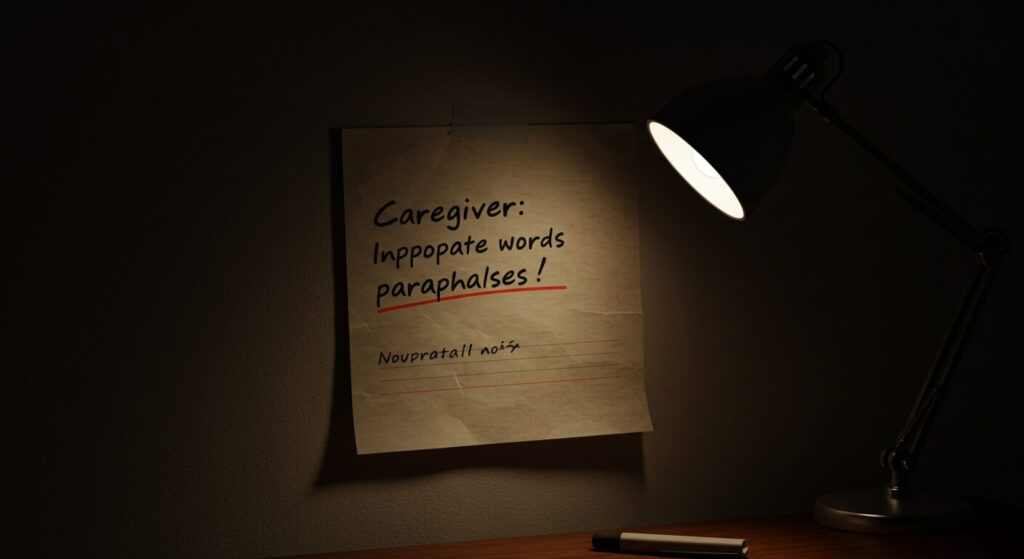
介護現場では、利用者様、ご家族、同僚など、様々な立場の方とコミュニケーションを取る必要があります。
言葉遣いを間違えると、相手を傷つけたり、信頼関係を損ねたりする可能性があります。
ここでは、具体的なNGワードの例と、適切な言い換え表現を紹介します。
利用者に対するNGワードと適切な言い換え
利用者様に対しては、特に丁寧な言葉遣いを心がける必要があります。
例えば、タメ口や命令口調は避け、「~してください」「~しましょう」といった敬意を払った表現を使いましょう。
また、利用者様を子供扱いするような言葉もNGです。
「おじいちゃん」「おばあちゃん」ではなく、「~様」「~さん」と名前でお呼びするようにしましょう。
また、身体的な特徴や認知症による行動などを揶揄するような言葉も厳禁です。
常に相手の尊厳を尊重し、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
家族に対するNGワードと配慮ある表現
ご家族は、利用者様の介護状況を心配されています。
そのため、ご家族への言葉遣いも非常に重要です。
例えば、「いつも大変ですね」といった同情の言葉は、かえってご家族を傷つける可能性があります。
「いつもありがとうございます」「ご協力いただき感謝いたします」といった感謝の言葉を伝えましょう。
また、ご家族の介護に対する考え方を否定するような言葉も避けるべきです。
ご家族の気持ちに寄り添い、共感する姿勢を見せることが大切です。
同僚に対するNGワードと円滑なコミュニケーションのための言葉
同僚との言葉遣いも、円滑な職場環境を築く上で重要です。
例えば、相手の能力を否定したり、人格を傷つけるような言葉は避けましょう。
また、相手の意見を頭ごなしに否定するのではなく、「~という考え方もありますね」「~についてもう少し詳しく教えていただけますか」といった、相手の意見を尊重する言葉遣いを心がけましょう。
常に相手への敬意を忘れず、建設的なコミュニケーションを意識することが大切です。
介護記録におけるNGワードと具体的な例文
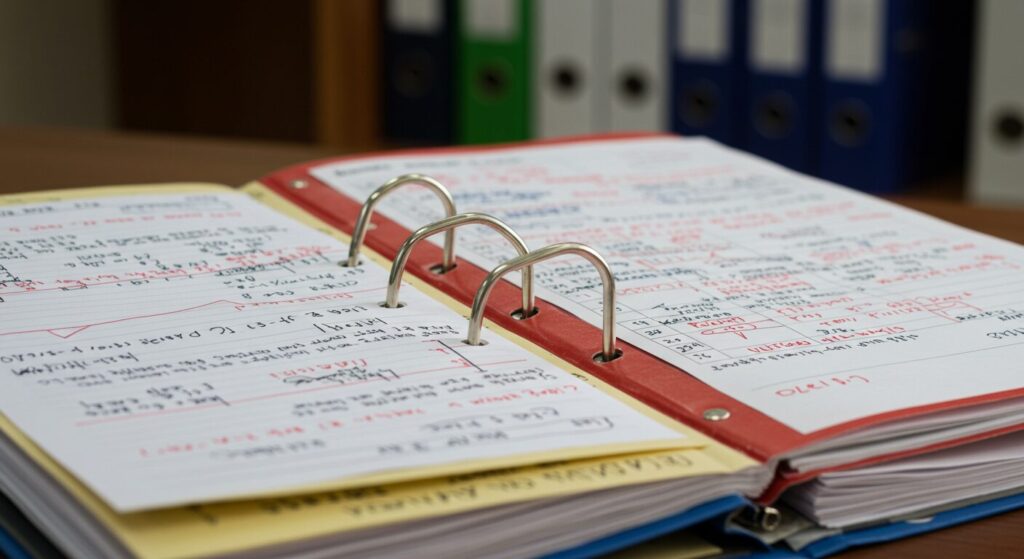
介護記録は、利用者様の状況を正確に把握し、適切な介護サービスを提供するために不可欠なツールです。
しかし、不適切な言葉遣いは、利用者様やご家族に誤解や不信感を与え、トラブルの原因となる可能性があります。
ここでは、介護記録におけるNGワードと、具体的な例文を交えて解説します。
介護記録では、客観的で正確な記録を心がけよう
介護記録では、主観的な表現や曖昧な言葉は避けなければなりません。
例えば、「~と思われる」「~かもしれない」といった推測や、「普通」「いつも通り」といった曖昧な言葉は、記録の信頼性を損ないます。
また、利用者様を侮辱したり、見下したりするような言葉も厳禁です。
例えば、「わがまま」「意地悪」といった言葉は、利用者様の人格を否定するものであり、記録として不適切です。
常に客観的な事実に基づき、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
状況別の介護記録の書き方(食事、排泄、トラブルなど)
介護記録は、食事、排泄、入浴、レクリエーションなど、様々な場面で作成されます。
それぞれの場面で、適切な記録の書き方を理解しておくことが重要です。
例えば、食事の記録では、「〇〇を△△g摂取」「食欲不振のため、〇〇を△△gのみ摂取」といったように、具体的な数値や状況を記録します。
排泄の記録では、「〇時〇分に排尿〇〇ml」「〇時〇分に排便〇〇g」といったように、時間や量を記録します。
トラブルが発生した場合は、「〇時〇分に転倒」「〇時〇分に利用者様同士で口論」といったように、状況を客観的に記録し、対応した内容も記録しておきましょう。
介護記録を書く上での5つのポイント
介護記録を作成する際は、以下の点に注意しましょう。
- 客観的な事実に基づき、正確に記録する
- 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して記録する
- 専門用語や略語は避け、誰が読んでも理解できる言葉を使う
- 利用者様のプライバシーに配慮し、個人情報保護を徹底する
- 記録は、利用者様やご家族に開示される可能性があることを意識する
これらの点に注意することで、信頼性の高い介護記録を作成することができます。
介護現場でNGワードを使ってしまった際の対処法と再発防止策
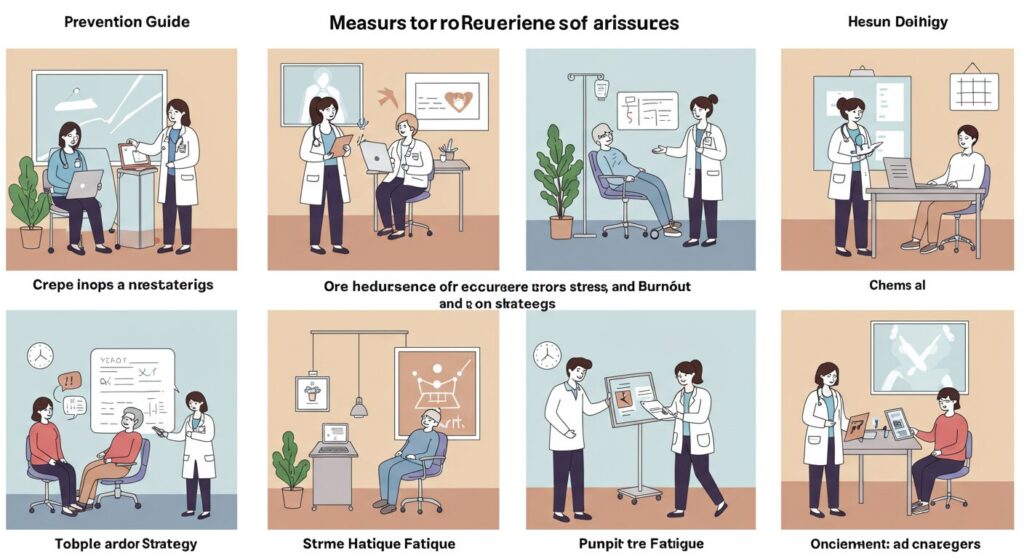
介護現場では、細心の注意を払っていても、うっかりNGワードを使ってしまうことがあります。
そのような場合、適切な対処と再発防止策を講じることが重要です。
ここでは、NGワードを使ってしまった際の対処法と、再発防止策について解説します。
NGワードを使ってしまった場合は、すぐに謝罪することが大切
まずは、相手に不快な思いをさせたことを素直に認め、謝罪の言葉を述べましょう。
その際、言い訳や責任転嫁は避け、誠意をもって謝罪することが重要です。
また、言葉だけでなく、態度や表情でも誠意を示すように心がけましょう。
可能であれば、後日改めて謝罪の機会を設けることで、より誠意が伝わるでしょう。
NGワードの再発防止には、具体的な対策を講じることが不可欠
まずは、どのような状況でNGワードを使ってしまったのかを振り返り、原因を特定しましょう。
その上で、以下のような対策を検討します。
- 言葉遣いに関する研修や勉強会に参加する
- 介護記録や関連書籍などを参考に、適切な言葉遣いを学ぶ
- 日頃から、利用者様やご家族の気持ちを想像する習慣をつける
- 同僚と協力し、お互いの言葉遣いをチェックし合う
これらの対策を継続的に行うことで、NGワードの再発防止に繋がります。
NGワードを使ってしまった場合は、一人で抱え込まず、周囲に相談することも大切
上司や同僚に相談することで、客観的な意見やアドバイスを得られるでしょう。
また、施設全体で協力体制を構築し、NGワードに関する情報を共有したり、研修を実施したりすることも有効です。
施設全体で意識を高め、協力し合うことで、より良い介護現場を作ることができます
利用者や家族とのコミュニケーションを円滑にするためのポイント

介護現場におけるコミュニケーションは、利用者様やご家族との信頼関係を築き、質の高い介護サービスを提供するために不可欠です。
ここでは、コミュニケーションを円滑にするための具体的なポイントを紹介します。
相手の気持ちを理解しようとする姿勢が、より良いコミュニケーションに繋がる
利用者様やご家族の話に耳を傾け、共感を示すことは、信頼関係を築く上で非常に重要です。
まずは、相手の話を遮らず、最後まで聞くことを心がけましょう。
話を聞く際は、相槌や頷き、アイコンタクトなどを通して、相手への関心を示すことが大切です。
また、相手の感情に寄り添い、「つらいですね」「大変でしたね」といった共感の言葉を伝えることで、相手は安心感を覚えるでしょう。
敬意を込めた言葉遣いと態度が大切
利用者様やご家族に対しては、常に敬意を込めた言葉遣いと態度で接することが重要です。
タメ口や命令口調は避け、「~様」「~さん」といった敬称を使い、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
また、相手の意見や考えを尊重し、否定的な言葉は避けるべきです。
言葉遣いだけでなく、笑顔や穏やかな表情、丁寧な身振り手振りなども、相手への敬意を示す上で重要です。
相手を尊重する姿勢が、信頼関係を深めるための土台となります。
信頼関係を築くには日頃の積極的なコミュニケーションが大事
信頼関係を築くためには、日頃からのコミュニケーションが重要です。
まずは、利用者様やご家族との会話を積極的に行い、相手のことをよく知るように努めましょう。
会話を通して、相手の趣味や好きなこと、過去の経験などを知ることで、共通の話題を見つけやすくなります。
また、相手の話に興味を持ち、積極的に質問することで、会話が弾み、親近感が生まれるでしょう。
日頃から積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係を築く努力が大切です。
介護現場でNGワードを避けるための研修や学習方法

介護現場でNGワードを避けるためには、日頃からの意識と学習が不可欠です。
ここでは、具体的な研修や学習方法、そして日頃から意識できる考え方について解説します。
施設内研修や外部セミナーを活用する
多くの介護施設では、言葉遣いに関する研修や勉強会が定期的に開催されています。
これらの研修では、NGワードの具体例や適切な言い換え表現、利用者様やご家族とのコミュニケーションのポイントなどを学ぶことができます。
また、外部の専門家を招いてセミナーを開催する施設もあります。
外部セミナーでは、より専門的な知識や技術を習得できるでしょう。
積極的に研修やセミナーに参加し、自身の言葉遣いを磨くことが大切です。
書籍やインターネットで学習する
書籍やインターネットでも、言葉遣いに関する情報を得ることができます。
書籍では、具体的な事例や言い換え表現、コミュニケーションのポイントなどが詳しく解説されています。
インターネットでは、専門家の記事や動画などを参考に、より実践的な知識を習得できるでしょう。
また、SNSなどで情報交換をすることも有効です。
他の介護職員の意見や経験を知ることで、自身の視野を広げることができます。
NGワードを使わないためには、日頃からの意識が重要
まずは、利用者様やご家族の気持ちを想像する習慣をつけましょう。
相手の立場に立って考えることで、どのような言葉が相手を傷つけるのかを理解できます。
また、常に丁寧な言葉遣いを心がけ、相手への敬意を忘れないようにしましょう。
言葉遣いは、日々の積み重ねで身につくものです。
常に意識し、実践することで、自然とNGワードを避けることができるようになります。
【Q&A】介護現場のNGワードに関してよくある質問

介護現場での言葉遣いに関する疑問や不安は、多くの介護職員が抱えています。
ここでは、NGワードに関するよくある質問に回答します。
NGワードを使ってしまった場合の対応方法は?
まずは、相手に不快な思いをさせたことを謝罪しましょう。
その際、言い訳や責任転嫁は避け、誠意をもって謝罪することが重要です。
また、言葉だけでなく、態度や表情でも誠意を示すように心がけましょう。
可能であれば、後日改めて謝罪の機会を設けることで、より誠意が伝わるでしょう。
その後は、再発防止のために、NGワードを使ってしまった状況を振り返り、原因を特定し、具体的な対策を講じることが大切です。
記録を書くときに、つい主観的な意見が入ってしまいます。
介護記録は、客観的な事実に基づき、正確に記録する必要があります。
そのため、主観的な意見や感情的な表現は避けましょう。
例えば、「〇〇さんはわがままだ」「〇〇さんはいつも不機嫌だ」といった表現は、記録として不適切です。
代わりに、「〇〇さんは〇〇を要求することが多い」「〇〇さんは〇〇の際に不機嫌な表情を見せる」といったように、具体的な行動や状況を客観的に記録するように心がけましょう。
また、記録を書く前に、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識することで、客観的な記録を作成しやすくなります。
高齢者の方とのコミュニケーションをとる上で大切なことはなんですか?
高齢者の方とのコミュニケーションでは、相手への敬意と共感を示すことが大切です。
まずは、相手の話に耳を傾け、共感する姿勢を示しましょう。
また、ゆっくりと話したり、大きな声で話したりするなど、相手に合わせた話し方を心がけることも重要です。
さらに、相手の過去の経験や思い出話などを聞き、共感することで、より深いコミュニケーションを築くことができます。
まとめ:介護現場で心がけたい言葉遣い
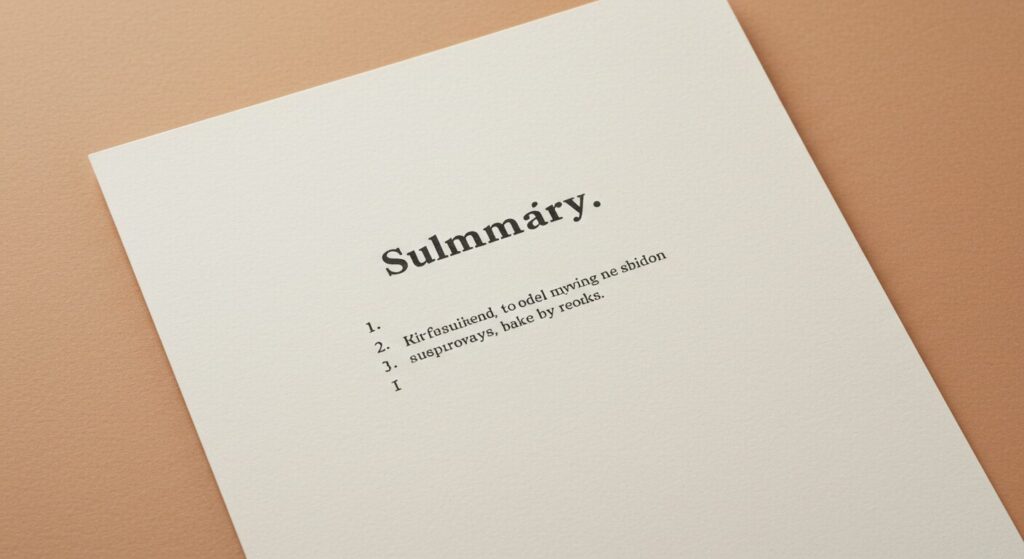
介護現場における言葉遣いは、利用者様やご家族との信頼関係を築き、質の高い介護サービスを提供するために非常に重要です。
NGワードを使ってしまうと、相手を傷つけたり、信頼関係を損ねたりするだけでなく、介護職員自身の評価や施設の評判にも悪影響を及ぼす可能性があります。
NGワードを避けるためには、日頃から丁寧な言葉遣いを心がけるとともに、研修や学習を通して知識を深めることが大切です。
また、利用者様やご家族とのコミュニケーションを円滑にするために、傾聴や共感、敬意を込めた言葉遣いを意識しましょう。
もしNGワードを使ってしまった場合は、すぐに謝罪し、再発防止に努めることが重要です。
一人で抱え込まず、周囲に相談し、協力体制を構築することも大切です。
この記事が、介護に関わる全ての人が適切な言葉遣いを意識し、より良い介護現場を作る一助となれば幸いです。