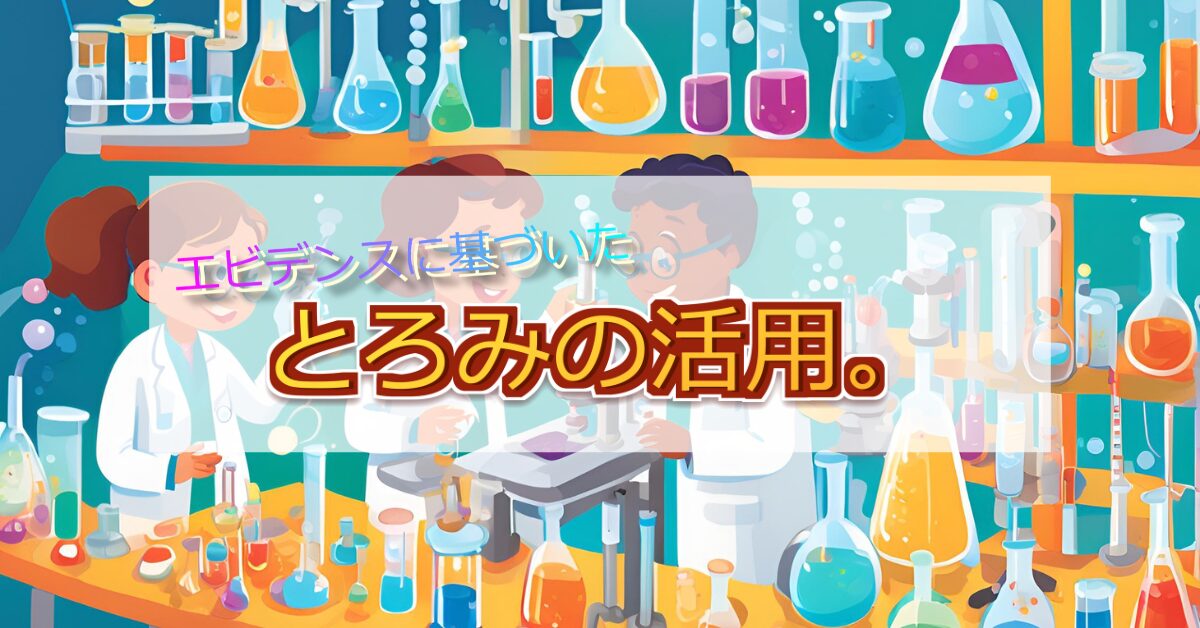介護の現場において、食事は単に栄養を摂取するだけでなく、生活の質(QOL)を維持する上でも非常に重要な要素です。特に、加齢や病気などで嚥下機能(飲み込む力)が低下している方にとって、食事にとろみをつけることは、安全でおいしい食事を提供する上で欠かせない配慮となります。とろみは、食べ物や飲み物を飲み込みやすくし、誤嚥を防ぐ役割を果たします。
この記事では、介護食におけるとろみの重要性から、とろみ剤の種類、選び方、つけ方、そして注意点までを徹底的に解説し、介護に携わる方々が日々の食事作りで役立てられる情報を提供します。
Contents
なぜ介護食にとろみが必要なのか?〜誤嚥を防ぐための重要な役割〜

介護食にとろみをつける最大の理由は、誤嚥(ごえん)を防ぐためです。誤嚥とは、食べ物や飲み物が誤って気管に入ってしまうことを指し、高齢者や嚥下障害を持つ方にとっては深刻な健康リスクとなります。
- 嚥下機能の低下: 加齢や脳血管疾患、神経系の病気など様々な要因により、食べ物を認識し、口に取り込み、咀嚼(そしゃく)し、咽頭を通過させて食道へ送り込むという一連の動作がスムーズに行えなくなることがあります。これが嚥下機能の低下です。
- 誤嚥のリスク: 嚥下機能が低下すると、食べ物や飲み物が気管に入りやすくなり、気管支炎や肺炎(特に誤嚥性肺炎)を引き起こす可能性が高まります。誤嚥性肺炎は、高齢者の死亡原因の一つとしても知られています。
- とろみの効果: とろみをつけることで、食べ物や飲み物がまとまりやすくなり、喉をゆっくりと通過するため、気管への侵入を防ぎ、誤嚥のリスクを大幅に軽減することができます。また、とろみによって食塊の形成が促進され、口から食道への移動がスムーズになります。
とろみ剤の種類と特徴〜用途に合わせて最適なものを選択〜

とろみ剤には、主に以下の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、食事の内容や対象者の状態に合わせて適切なものを選びましょう。
デンプン系とろみ剤〜手軽さと経済性が魅力〜
- 特徴: 片栗粉やコーンスターチなどのデンプンを主成分としており、安価で広く使用されています。比較的短時間でとろみがつきやすいのが特徴です。
- 注意点: 温度変化や時間の経過によって粘度が変化しやすく、唾液中のアミラーゼという酵素によって分解され、とろみが弱まることがあります。温かい食品ではとろみがつきにくい場合もあります。
- おすすめ: 手軽にとろみをつけたい場合や、比較的短時間で食べきる場合に適しています。冷たい飲み物や、すぐに食べる料理に向いています。
グアガム系とろみ剤〜少量でしっかりとしたとろみ〜
- 特徴: グア豆由来の多糖類を主成分としており、少量で高い粘度を得られるのが特徴です。
- 注意点: ダマになりやすく、混ぜ方に注意が必要です。また、独特の風味を感じる場合があります。
- おすすめ: 少量でしっかりとしたとろみをつけたい場合や、水分量の少ない食品に適しています。
キサンタンガム系とろみ剤〜安定性と風味の良さ〜
- 特徴: 微生物の発酵によって生成される多糖類を主成分としており、安定性が高く、温度変化や時間の経過による粘度変化が少ないのが特徴です。味や匂いがほとんどないため、食品本来の風味を損ないにくいです。
- 注意点: 比較的高価な場合があります。
- おすすめ: 味や匂いに敏感な方や、温かい飲み物、時間の経過による変化を避けたい場合、また、様々な食品に安定したとろみをつけたい場合に適しています。
とろみ剤の選び方〜成分、使用方法、そして好みで選ぶ〜

とろみ剤を選ぶ際には、以下の点を考慮しましょう。
成分で選ぶ〜アレルギーにも配慮を〜
- デンプン系、グアガム系、キサンタンガム系など、成分によってとろみのつき方や食感、風味が異なります。
- 食品本来の風味を損ねないよう、味や匂いの少ないものを選ぶと良いでしょう。
- 食物アレルギーのある方は、成分をよく確認し、アレルゲンが含まれていないかを確認することが重要です。
使用方法で選ぶ〜使いやすさも重要なポイント〜
- とろみ剤は、飲み物や食べ物に加えて混ぜることでとろみがつきます。混ぜ方や時間によってもとろみの具合が変わるため、各製品の適切な使用方法に従いましょう。
- 溶けやすさ、ダマになりにくさ、混ぜやすさなど、使いやすさも考慮すると良いでしょう。
好みで選ぶ〜とろみの強さや食感の好み〜
- とろみの強さの好みは人それぞれです。薄いとろみ、中間のとろみ、濃いとろみなど、対象者の好みに合わせて調整できるものを選びましょう。
- 実際に少量を試してみて、使いやすいもの、好みの食感になるものを選ぶのがおすすめです。
正しいとろみのつけ方〜ダマを防ぎ、均一なとろみを実現〜

とろみをつける際には、以下の手順と注意点を守り、ダマを防ぎ、均一なとろみをつけましょう。
基本的な手順〜混ぜながら加えるのが基本〜
- コップや器に飲料や調理済みの食品を入れます。
- スプーンやフォークなどで飲料や食品をかき混ぜながら、少量ずつとろみ剤を加えます。
- 20〜30秒ほど、しっかりと混ぜ合わせます。
- とろみがつくまで、必要に応じて少し待ちます。
ダマにならないための工夫〜混ぜ方と順番が重要〜
- とろみ剤を加える際は、必ずかき混ぜながら少量ずつ加えることで、ダマになるのを防ぐことができます。
- ダマができてしまった場合は、取り除くか、再度よく混ぜて溶かしましょう。
- 泡立て器を使用すると、より均一に混ぜることができます。特に、グアガム系を使用する場合は有効です。
とろみの状態を確認する〜適切なとろみを見極める〜
- スプーンで持ち上げてみて、流れ落ちる様子を確認しましょう。適切なとろみは、ゆっくりと流れ落ちるか、スプーンにまとわりつく程度です。
- 薄いとろみ、中間のとろみ、濃いとろみなど、対象者の嚥下状態や好みに合わせて適切な状態になっているか確認しましょう。
- 必要に応じて、とろみ剤の量を微調整しましょう。
とろみをつける際の注意点〜安全な食事のために〜

とろみをつける際には、以下の点に注意が必要です。
つけすぎに注意〜逆に飲み込みにくくなることも〜
- とろみをつけすぎると、逆に飲み込みにくくなることがあります。特に、濃すぎる場合は喉に詰まる危険性があります。
- 食べる方の状態(嚥下能力)に合わせて、適切な量を使用しましょう。
- 最初は少なめに加え、様子を見ながら少しずつ調整するのがおすすめです。
温度変化に注意〜とろみの状態が変わる場合も〜
- とろみ剤の種類によっては、温度変化によって粘度が変わる場合があります。温かい飲み物や冷たい飲み物など、温度に合わせてとろみの状態を確認しましょう。
- 作り置きする場合は、時間の経過による変化も考慮し、食べる前に再度とろみの状態を確認するようにしましょう。
食材との相性〜酸性の強いものには注意〜
- 食材によっては、とろみがつきにくい場合があります。特に、酸性の強い飲み物(オレンジジュースなど)や、牛乳などのタンパク質を多く含む飲み物は、とろみがつきにくい傾向があります。
- 必要に応じて、とろみ剤の種類を変えたり、量を調整したり、温めてから加えるなどの工夫をしましょう。
まとめ〜安全でおいしい食事のために〜

介護食におけるとろみは、嚥下機能が低下している方々にとって、安全な食事を提供するための重要な要素です。適切なとろみ剤を選び、正しい方法で使用することで、誤嚥を防ぎ、食事の時間を安心して楽しむことができます。この記事を参考に、日々の介護食作りに役立てていただき、食事の時間がより豊かなものとなることを願っています。