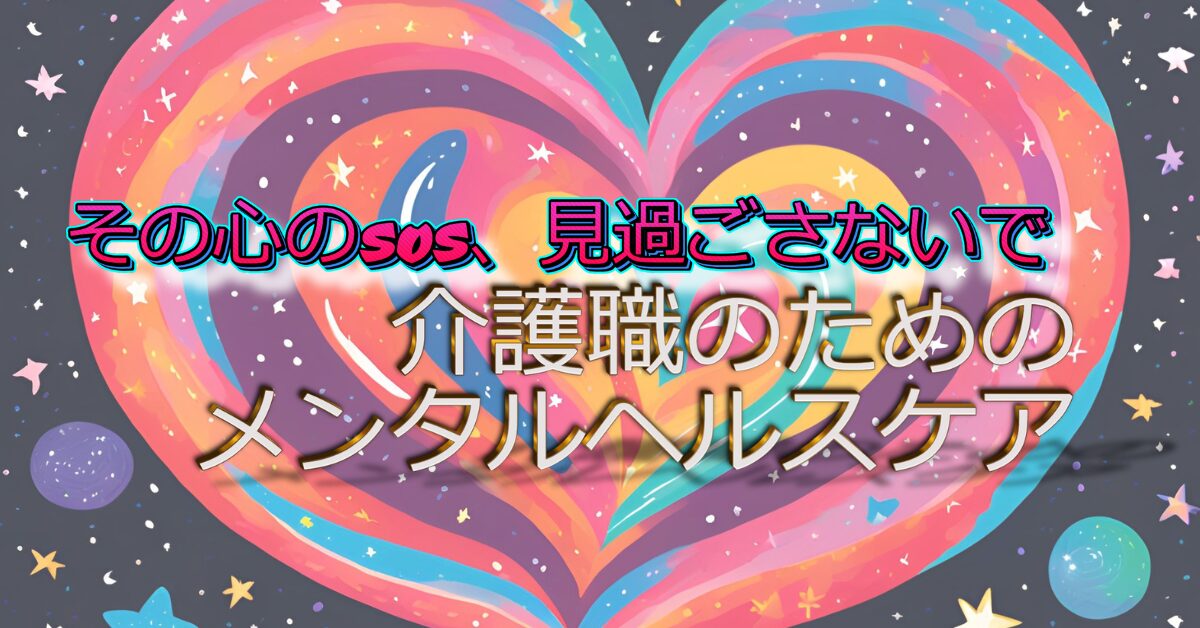高齢化が進む日本において、介護職は社会を支える重要な役割を担っています。
しかし、その仕事は決して楽なものではありません。利用者様の生活を支える喜びがある一方で、身体的な負担はもちろんのこと、精神的な負担も非常に大きいのが現状です。
- 職場の人間関係に悩んでいる
- 仕事の責任の重さに押しつぶされそう
- 頑張っても評価されないと感じる
- 夜勤続きで心身ともに疲弊している
- 利用者様やご家族とのコミュニケーションに苦労している
もし、一つでも当てはまるなら、あなたは一人ではありません。多くの介護職の方が、同じような悩みを抱えています。
厚生労働省の調査によると、仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合は依然として半数を超えています。
特に介護現場では、人手不足や業務の多忙さ、責任の重さなどが重なり、メンタルヘルスの不調を訴える方が少なくありません。
この記事では、介護職が直面するメンタルヘルスの問題に焦点を当て、その原因と具体的な対策を詳しく解説します。
大切なのは、問題を認識し、適切な対応を取ることです。
この記事が、あなたの心の負担を少しでも軽くし、より健康的に働くための一助となれば幸いです。ぜひ、最後までお読みください。
この記事でわかること
- 介護職がメンタルヘルスを崩しやすい原因
- メンタルヘルスの不調によって現れる具体的な症状
- メンタルヘルスを維持するための具体的な対策
この記事を書いた人

ハロー介護職
適応障害と付き合いつつ、日々介護現場で高齢者と向き合う一人の介護職。
X(旧Twitter)やTikTokで自信の介護感や疑問を投げかける活動をしています。
介護系記事監修の仕事もしています。
お仕事の相談はX(旧Twitter)のDMにて受け付けております。
お気軽にご相談ください。
Contents [hide]
介護職がメンタルヘルスを崩しやすい原因

介護職は、高齢化社会において必要不可欠な存在であり、社会貢献性の高い仕事です。
しかし、その仕事内容は多岐にわたり、身体的にも精神的にも大きな負担を伴うため、他業種と比べてもストレスを感じやすい環境にあります。
その背景には、以下のような要因が複雑に絡み合っています。
職場の人間関係の複雑さ
介護現場では、同僚や上司といった職場内の人間関係だけでなく、利用者様一人ひとりの個性や状態に合わせた対応、さらにはそのご家族とのコミュニケーションも非常に重要になります。
それぞれの立場や考え方の違いから、人間関係のトラブルが生じやすく、それが大きなストレスにつながることがあります。
職員間のコミュニケーション不足
業務の忙しさから、職員間の情報共有や意思疎通が不足しがちです。
報告・連絡・相談がスムーズに行われないことで、誤解や不信感が生じ、人間関係の悪化につながることがあります。
また、日々の業務で手一杯になり、ゆっくりとコミュニケーションを取る時間がないことも、人間関係の希薄化を招く要因となります。
利用者様やご家族からの過度な要求
利用者様やご家族は、介護サービスに対して様々な期待を持っています。
中には、介護職員の能力を超えた要求や、理不尽なクレームを突きつける方もおり、それが介護職員の精神的な負担となります。
また、認知症の方への対応など、コミュニケーションが難しいケースも多く、精神的な疲労につながります。
チームワークの欠如
介護はチームで行う仕事です。しかし、職員間の連携が不足していると、業務がスムーズに進まず、ミスやトラブルの原因となります。
また、責任の所在が曖昧になり、個々の職員の負担が増大することもあります。
良好なチームワークを築くためには、日頃からのコミュニケーションと情報共有が不可欠です。
仕事内容の負担の大きさ
介護の仕事は、利用者を抱きかかえるなどの身体的な負担が大きいだけでなく、常に利用者の安全に気を配り、適切なケアを提供しなければならないという緊張感を伴う精神的な負担も大きい仕事です。
夜勤や不規則な勤務時間も、生活リズムの乱れを引き起こし、心身の健康に悪影響を与えます。
- 身体的な介助の負担: 利用者の移乗介助や入浴介助など、身体的な負担が大きい業務が多く、腰痛や肩こりなどの身体的な不調を抱える職員も少なくありません。特に、人手不足の現場では、一人当たりの業務量が増え、身体への負担がさらに大きくなります。
- 夜勤や不規則な勤務時間: 24時間体制の施設では、夜勤や不規則なシフト勤務が避けられません。生活リズムが乱れることで、睡眠不足や自律神経の乱れを引き起こし、心身の健康に悪影響を与えます。また、家族や友人との時間も取りづらくなり、孤立感を感じることもあります。
- 責任の重さ: 介護職は、利用者の生命と安全を預かる責任の重い仕事です。常に細心の注意を払い、適切なケアを提供しなければなりません。万が一、事故やトラブルが発生した場合は、大きな精神的負担となります。
評価制度や給与への不満
介護職は、営業職のように成果を数値で明確に評価することが難しいため、職員がどれだけ努力しても、その頑張りや成果が正当に評価されていないと感じることがあります。
また、他業種と比べて給与水準も決して高いとは言えず、それがモチベーションの低下につながり、離職を考える要因となることもあります。
- 評価基準の不明確さ: どのような基準で評価されているのかが不明確だと、職員は目標を持ちにくく、モチベーションを維持することが難しくなります。また、評価結果に納得がいかない場合、不満や不信感を抱くことにつながります。
- 努力が反映されない評価制度: 一生懸命に利用者のケアに取り組んでも、それが給与や昇給に反映されないと感じると、職員は努力する意欲を失ってしまいます。日々の業務に対するモチベーションの低下は、メンタルヘルスにも悪影響を与えます。
- 給与水準への不満: 仕事の責任や負担に見合った給与が支払われていないと感じる場合、不満が募り、仕事への意欲を失うだけでなく、生活への不安も抱えることになります。
メンタルヘルスの不調によって現れる症状

メンタルヘルスの不調は、心と体に様々なサインとして現れます。
これらの症状は、放置すると日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、より深刻な精神疾患につながる可能性もあります。
早期に気づき、適切な対応を取ることが非常に重要です。
以下では精神面、身体面、行動面に分けて、具体的な症状を詳しく解説します。
精神的な症状
気分の落ち込み、不安感、イライラ、集中力の低下など、精神的な症状は、日常生活における様々な活動に支障をきたすことがあります。
些細なことで悲しくなったり、理由もなく不安になったりする状態が続く場合は、注意が必要です。
- 気分の落ち込みや憂鬱感: 何をするにも気が進まない、何をしても楽しくない、といった状態が続くことがあります。些細なことで涙もろくなったり、将来に対して悲観的な考えを持つようになったりすることもあります。
- 不安感や焦燥感: 何かに対して漠然とした不安を感じたり、理由もなくそわそわしたり、落ち着かなくなったりすることがあります。些細なことでも過剰に心配したり、将来に対して強い不安を感じたりすることもあります。
- 集中力や意欲の低下: 物事に集中できなくなり、仕事や家事、勉強などに支障をきたすことがあります。以前は簡単にできていたことが難しく感じたり、物事を先延ばしにするようになったりすることもあります。また、何事にも意欲がわかなくなり、何もする気が起きないという状態になることもあります。
- イライラや怒りっぽくなる: ちょっとしたことでイライラしたり、怒りっぽくなったりすることがあります。周囲の人に当たり散らしたり、感情のコントロールが難しくなったりすることもあります。
身体的な症状
不眠、食欲不振、頭痛、肩こりなど、身体的な症状もメンタルヘルスの不調の重要なサインです。
これらの症状は、精神的なストレスが身体に影響を及ぼしている可能性を示唆しています。
- 不眠や睡眠不足: なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、朝早く目が覚めてしまうなど、睡眠に関する問題が生じることがあります。十分な睡眠が取れないと、日中の眠気や倦怠感、集中力の低下につながります。
- 食欲不振や過食: 食欲がなくなったり、逆に過食になったりすることがあります。ストレスから食べ物に走ってしまう、逆に何も食べられなくなってしまうなど、食生活に変化が現れることがあります。
- 頭痛や肩こり: 慢性的な頭痛や肩こり、首の痛みなどを感じるようになることがあります。精神的な緊張が筋肉の緊張につながり、これらの症状を引き起こすと考えられています。
- 胃腸の不調: 胃痛、吐き気、便秘、下痢など、胃腸の調子が悪くなることがあります。ストレスが自律神経のバランスを崩し、消化器系の機能に影響を及ぼすためと考えられます。
行動の変化
これまで楽しめていたことに興味がなくなる、人に会いたくなくなる、といった行動の変化も、メンタルヘルスの不調を示すサインです。
周囲から見ても変化が分かりやすい場合もあります。
- 趣味や好きなことへの興味喪失: これまで熱中していた趣味や好きなことに全く興味がなくなってしまうことがあります。何をやっても楽しくない、何もする気が起きないという状態になることもあります。
- 人との交流を避けるようになる: 外出を控えたり、友人や家族との交流を避けるようになったりすることがあります。人と会うのが億劫になり、家に引きこもりがちになることもあります。
- 仕事への意欲低下: 仕事に行くのが辛くなったり、遅刻や欠席が増えたりすることがあります。仕事中も集中できず、ミスが増えたり、周囲とのコミュニケーションを避けたりするようになることもあります。
- 飲酒や喫煙の増加: ストレスを紛らわせるために、飲酒量が増えたり、喫煙本数が増えたりすることがあります。
メンタルヘルスを維持するための具体的な対策

メンタルヘルスの不調を感じたら、放置せずに早めに対策を講じることが何よりも大切です。
早期に対処することで、症状の悪化を防ぎ、より健康的な生活を送ることができます。
以下に、今日からでも実践できる具体的な対策をご紹介します。
休息とリフレッシュ
日々の仕事で疲れた心と体を癒すためには、質の高い休息とリフレッシュが不可欠です。
十分な睡眠を取り、趣味やリラックスできる時間を意識的に作るように心がけましょう。
心身のリフレッシュは、蓄積したストレスを解消し、メンタルヘルスの維持に非常に効果的です。
質の高い睡眠を確保する
毎日同じ時間に寝起きし、規則正しい生活リズムを保つことが大切です。
寝る前にはカフェインの摂取を避け、リラックスできる環境を整えましょう。
ぬるめのお風呂に入る、アロマを焚く、軽いストレッチをするなども効果的です。
睡眠時間は個人差がありますが、7〜8時間を目安に確保するように心がけましょう。
趣味や好きなことを楽しむ時間を作る
仕事以外の時間で、自分が楽しいと感じることを行うことで、気分転換になり、ストレスを発散することができます。
音楽を聴く、映画を見る、読書をする、スポーツをする、旅行に行くなど、自分が心から楽しめることを見つけて、積極的に取り入れるようにしましょう。
リラックスできる環境を作る
自宅では、落ち着ける空間を作るように心がけましょう。
部屋の掃除をする、好きな音楽をかける、アロマを焚くなど、五感を心地よく刺激することで、リラックス効果を高めることができます。
また、自然の中で過ごすことも、心身のリフレッシュに効果的です。
休日は公園を散歩したり、自然豊かな場所へ出かけたりするのも良いでしょう。
周囲への相談
一人で悩みを抱え込まず、信頼できる人に相談することも、メンタルヘルスを維持する上で非常に重要です。
信頼できる同僚や上司、家族や友人に悩みを打ち明けることで、気持ちが楽になることがあります。
また、必要に応じて、専門機関への相談も検討しましょう。客観的なアドバイスを受けることで、新たな視点や解決策が見つかるかもしれません。
- 同僚や上司に相談する: 同じ職場で働く同僚や上司は、仕事の状況や悩みを理解してくれる可能性が高いです。気軽に相談できる関係性を築いておくことが大切です。職場に相談窓口がある場合は、そちらを利用するのも良いでしょう。
- 家族や友人に話を聞いてもらう: 家族や友人は、あなたのことをよく知っているため、親身になって話を聞いてくれるでしょう。他愛もない話をするだけでも、気持ちが楽になることがあります。
- 専門の相談窓口を利用する: 職場の相談窓口、地域の保健所や精神保健福祉センター、民間の相談機関など、様々な相談窓口があります。専門家のアドバイスを受けることで、問題の解決につながることがあります。一人で抱え込まず、積極的に利用することを検討しましょう。
職場環境の改善
メンタルヘルスの不調の原因が職場環境にある場合は、根本的な解決のためには、職場環境の改善に取り組むことが重要です。
職場の人間関係や労働環境に問題がある場合は、改善を求めることも重要です。
管理職や人事担当者に相談し、より働きやすい環境づくりに協力しましょう。
- 職場環境の問題点を明確にする: どのような点がストレスの原因になっているのかを具体的に書き出すことで、問題点を明確にすることができます。例えば、「人手不足で業務過多になっている」「上司のパワハラがある」「同僚とのコミュニケーションが不足している」など、具体的に記述することで、改善策を検討しやすくなります。
- 管理職や人事に相談する: 問題点を明確にした上で、管理職や人事担当者に相談し、改善を求めましょう。問題を共有し、協力して解決策を探ることが大切です。
- 労働組合や外部機関に相談する: 職場内で問題を解決するのが難しい場合は、労働組合や外部の労働相談機関に相談することも検討しましょう。客観的な立場からのアドバイスやサポートを受けることで、問題解決につながることがあります。
相談できる窓口と支援制度

メンタルヘルスの問題は、決して一人で抱え込まず、専門機関や支援制度を積極的に活用することが大切です。
適切なサポートを受けることで、症状の改善や問題の解決につながるだけでなく、より良い生活を送るためのヒントを得られることもあります。
以下に、相談できる窓口と活用できる支援制度について詳しく解説します。
地域の相談窓口
各自治体には、地域住民のメンタルヘルスをサポートするための様々な相談窓口が設置されています。
専門の相談員が、個々の状況に合わせて親身になって相談に乗ってくれます。
気軽に相談することで、気持ちが楽になったり、問題解決の糸口が見つかったりすることもあります。
- 保健所や精神保健福祉センター: 保健所は、地域住民の健康増進を目的とした行政機関であり、精神保健福祉センターは、精神保健に関する専門的な相談や支援を行っています。精神保健福祉士や医師などの専門家がおり、電話相談や面接相談、デイケアなどのサービスを提供しています。
- 地域の医療機関: 地域の精神科や心療内科などの医療機関でも、メンタルヘルスの相談を受け付けています。医師の診察を受けることで、適切な診断や治療を受けることができます。かかりつけ医に相談してみるのも良いでしょう。
- 民間の相談機関: 民間の相談機関では、カウンセラーや心理士などの専門家が、個別の相談に応じています。電話相談やオンライン相談、対面相談など、様々な形式で相談を受け付けている機関もあります。
職場の相談窓口
職場によっては、従業員のメンタルヘルスをサポートするための相談窓口を設けている場合があります。
気軽に相談できる環境が整っているか確認してみましょう。相談することで、職場環境の改善につながることもあります。
- 社内相談窓口の有無を確認: 企業によっては、従業員向けの相談窓口を社内に設置している場合があります。人事部や労務担当部署に問い合わせて、相談窓口の有無や利用方法を確認してみましょう。
- 産業医やカウンセラーとの面談: 企業によっては、産業医やカウンセラーが定期的に職場を訪問し、従業員の健康相談に応じています。面談を希望する場合は、人事部や労務担当部署に申し出てみましょう。
- 労働組合への相談: 労働組合は、労働者の権利を守るための組織です。職場環境や労働条件に関する問題だけでなく、メンタルヘルスの問題についても相談することができます。
支援制度の活用
国や自治体では、メンタルヘルスに関する様々な支援制度が用意されています。
これらの制度を有効に活用することで、経済的な負担を軽減しながら適切なサポートを受けることができます。
制度の内容や申請方法については、自治体の窓口や厚生労働省のウェブサイトなどで確認することができます。
- 自立支援医療制度: 精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担額を軽減する制度です。通院医療費の自己負担額が原則1割になります。
- 精神障害者保健福祉手帳: 精神障害のある方が、様々な福祉サービスを受けるために必要な手帳です。障害の程度によって等級が分かれており、受けられるサービスの内容も異なります。
- 傷病手当金: 病気やケガで会社を休んでいる間、健康保険から給与の一部が支給される制度です。精神疾患も対象となります。
- その他、各自治体独自の支援制度: 各自治体では、独自のメンタルヘルス支援制度を設けている場合があります。お住まいの自治体のウェブサイトや窓口で確認してみましょう。
まとめ|介護職のメンタルヘルスを守るために

この記事のポイント
- 早期発見・早期対応: メンタルヘルスの不調は、早期に気づき、適切な対応を取ることが大切です。
- 周囲への相談: 一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談しましょう。
- 適切な休息とリフレッシュ: 質の高い睡眠を確保し、趣味やリラックスできる時間を持ちましょう。
- 職場環境の改善: 必要に応じて、職場環境の改善を求めましょう。
- 支援制度の活用: 国や自治体の支援制度を有効に活用しましょう。
介護職は、高齢化社会を支える重要な役割を担う、非常にやりがいのある仕事です。
しかし、その一方で、身体的な負担はもちろんのこと、精神的にも大きな負担がかかる仕事でもあります。
職場の人間関係、仕事内容の負担、評価制度や給与への不満など、様々な要因が複雑に絡み合い、メンタルヘルスの不調を引き起こす可能性があります。
メンタルヘルスの不調は、精神面だけでなく、身体面や行動面にも様々な症状として現れます。
気分の落ち込みや不安感、不眠や食欲不振、趣味への興味喪失など、これらのサインに早期に気づき、適切な対応を取ることが重要です。
もし、メンタルヘルスの不調を感じたら、決して一人で抱え込まず、周囲に相談したり、専門機関や支援制度を活用したりすることを検討してください。
休息とリフレッシュを心がけること、信頼できる人に悩みを打ち明けること、職場環境の改善を求めることなど、具体的な対策を講じることで、メンタルヘルスを維持し、より健康的に働くことができるはずです。
この記事では、介護職のメンタルヘルスに関する問題とその対策について解説しました。
この情報が、介護職の皆様が心身ともに健康で、長く仕事を続けられるための一助となれば幸いです。
ご自身の心と体を大切にしながら、長く介護の仕事に従事していただけることを心より願っております。